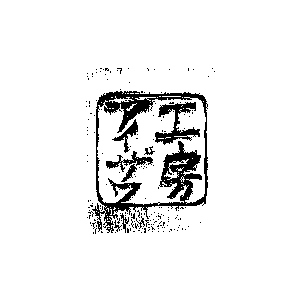伝統と歴史の宮島で
瀬戸内海に浮かぶ日本三景の一つ、宮島は世界文化遺産に登録された厳島神社や牡蠣や穴子めしなどのグルメも楽しめる伝統と歴史が息づく土地です。その宮島のなかでも代表的な伝統工芸品として全国的に広く知られているのが「杓子(しゃくし)・杓文字(しゃもじ)」です。板前用語では「木製杓文字」のことを「宮島」と呼ぶくらい高名です。本来「杓子」は飯または汁などの食物をすくいとる道具を指し、「杓文字」は特に飯をよそう道具とされていますが、宮島では一般的な「杓文字」のことも「杓子」と呼びます。宮島発祥の宮島杓子の伝統を今に受け継ぎ、現在も木製杓子を手づくりし続ける宮島工芸製作所さんは、厳島神社に程近い、広島県廿日市市宮島町の地で明治中頃から木製杓子を製造しています。
宮島杓子の誕生
今から約220年以上前に神泉寺の修行僧であった誓真(せいしん)が、現在の宮島のしゃもじの原型となった「宮島杓子(みやじましゃくし)」を考案したと伝えられています。宮島は神が宿る島のため耕作は禁止されていました。そこで誓真は島に従事する人々が空いた時間にできることは無いかと、宮島の神様の一柱「弁天様(弁財天)」が持っている「琵琶(びわ)」にヒントを得て、美しい曲線の杓子を御山の神木を使って作ることを島の人々に教えます。これが宮島杓子のはじまりです。「この神木の杓子で御飯をいただけば、ご神徳を蒙り福運をまねく」という、誓真の高徳とともに、宮島杓子は広く知られるようになり、誓真は宮島の発展に貢献した人として知られています。しゃもじはご飯をよそうだけの実用的な機能の他にも、「縁起物」でもあることをご存知でしょうか?高校野球の甲子園で広島県代表の応援に「しゃもじ」が使われているのは今ではお馴染みとなっています。それは、しゃもじの「飯(めし)取る(とる)」という動作から、「敵をめしとる」「幸せをめしとる」という言葉に掛けているからなのです。また弁財天は、もともと川の女神で、川の流れる音とその様子の連想から弁舌、音楽などの芸術に加えて、財運や勝運、招福も併せもった幅広いご利益がある縁起の良い神様です。それゆえ「宮島しゃもじ」は縁起が良いものとされています。
杓子にはヤマザクラ
杓子の原材料には、主に広島県産のヤマザクラを使用しています。木のまちとして知られる廿日市市(はつかいちし)は西日本有数の木材集積地があり、同市の材木屋さんから質の良い木材を選別して、仕入れることができます。こうして良質な木材を丸太で仕入れた後、板状に製材し約3~4ヶ月程しっかり乾燥させて、しゃもじ等の形を書き入れ、帯鋸盤と呼ばれる木材を切る鋸(のこぎり)で荒くカットします。ヤマザクラは、堅く弾力がありキメが細かくて丈夫という特長があります。そのため長く使うことができて、使えば使うほど木の色合いは赤みを増して味わいが出てきます。

全ての工程が手仕事


自社で独自に作った面取り盤用の専用冶具(固定しながら削る装置)で、上から見た形から整えていきます。次に表面→背面と更に形を整えていきます。ここまでの工程で大体の形が出来上がり、最後に荒削りの研磨→仕上げの研磨を行って、検品・修正の工程を経てようやく宮島杓子が出来上がります。形が美しいだけでなく、手に持ったときの優しい感覚がとても心地が良い宮島工芸製作所さんの杓子は、木の質だけでなくひとつひとつ丁寧に研磨され、愛情を持って作られたのだと感じる逸品で、長く大切に使いたい!と思わせてくれます。宮島工芸製作所さんがつくり出す道具は使っていくことで自分の手に馴染み、使った月日と共に深みを感じられるのが魅力のひとつです。
宮島工芸製作所の作り手のこと

宮島工芸製作所さんはご家族を中心に熟練の職人など、宮島杓子づくりに従事されている8名の会社です。全て職人による手作りのため、一日にできる杓子は限られています。作業は完全分業制なので、個々の技術が向上し、おのずと品質向上にも繋がっているそうです。最終工程の磨きや調整、検品はベテランの職人が行い、宮島杓子のブランド品質を守り続けています。宮島工芸製作所さんでは、丈夫で機能的な、気負わず使い込んでいける道具を目標に、日々の商品作りに取り組んでいます。こうしたものづくりに対する愛情が商品に伝わり、それを手に取った私たちがその思いを受けとる。この先もずっと、技術も愛情も未来に繋げていけるよう、私たちも微力ながらお伝えしていくことで何かお手伝いができればと思います。
宮島工芸製作所の商品一覧
 みそ・すしヘラ 16cm みそ・すしヘラ 16cm¥660 |  丸柄マル杓子 20cm 丸柄マル杓子 20cm¥1,320 |  丸柄ナナメ杓子 20cm 丸柄ナナメ杓子 20cm¥1,320 |
 ナナメターナー 30cm ナナメターナー 30cm¥1,100 |  ナナメターナー穴あき 30cm ナナメターナー穴あき 30cm¥1,100 |  特上直角お玉 30cm 特上直角お玉 30cm¥3,300 |