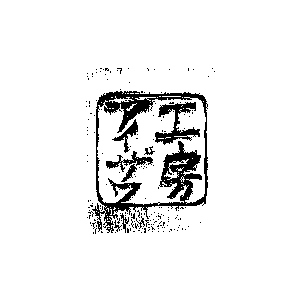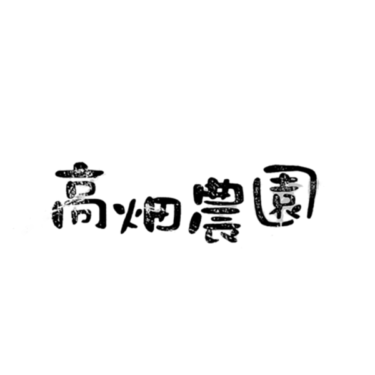株式会社ヤマキ
古くから日本人の暮らしに親しまれてきた竹製品を大分県別府市で発信し続ける雅竹さん。昔の人は、ひとつのものを永く大切に使う習慣がありました。でも現在は…。便利なものがあふれている今だからこそ、”ひとつのものを大切に使う”という価値観を見直すときがきているとの考えから、使い込むほどに艶を増し、自分だけの経年変化を愉しめる竹製品を日々作り続けられています。「古きを知り、新しさを知る」精神で日々ものづくりされています。今後は一つで二つ以上の機能を備えた商品開発を目指されていくとのこと。これもまた愉しみです。
画像提供元:株式会社ヤマキ
画像提供元:株式会社ヤマキ

1. 湯けむりが立ち上がる大分県別府市
大分県別府市では、町中湯けむりが立ち上がるほどのご存知温泉地です。また九州は竹が多く採れる土地柄で、九州北部では主に真竹、南部では孟宗竹が育生されています。室町時代に行商に使う籠が生産されるようになり、江戸時代になると別府が日本一の温泉地として有名になり、日本各地から湯治客が訪れる。滞在中に使う飯籠、米あげざるといった竹の生活用品や竹の盆ざるに好きな野菜や玉子をのせて、温泉の蒸気で蒸すという地獄蒸しなど、自宅に持ち帰りたいとの声から盆ざるの人気は広まり、別府竹細工が広く日本中に知られるようになった。これだけ竹細工が盛んなのは、温泉に由来するというから驚きです。
2. 真竹のこと
真竹(まだけ)は、10~20メートルの高さがあり、直径5~15センチ程度になる竹。筍は少し苦みがあることから苦竹と書く事もある。節間が長いのが特徴で粘り、しなりがあり日本の竹の中では竹製品、竹細工、竹工芸、クラフトなどの竹材料として最適とされています。青々とした色合いも美しく、正月飾りや青竹酒器などの青竹細工としても使われるが、油抜きをすることで白竹として使われることが多い。
3. 孟宗竹のこと
孟宗竹(もうそうちく)はもともとは中国原産で、雪の寒い日に年老いた母親のために筍を掘りにいった孟宗という人物にちなんで名付けられた。中国から江戸時代に日本に入ってきた竹で最初に植えられたのが京都という説と鹿児島説との二つある。国内の竹では最大の大きさで10~20メートル高さ、直径は8~20センチ程度になる。身の厚みがあるので、削りだしてカトラリーや竹しゃもじ、太い直径を活かした竹細工に用いられることが多い。
雅竹の作り手のこと
竹は1日で1mも伸びることのある成長力です。しなやかで丈夫、裂きやすい加工上の適性から古くから日本の暮らしを支えてきました。自然環境を整えるためにも竹を山から切り出すことは理にかなっています。それらを農具や生活に必要な道具として各家庭で作り、使ってきたと言います。だからこそ、手のうまい作り手の方がたくさんいらっしゃる土地柄なのだと思います。